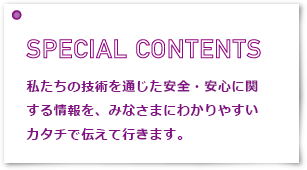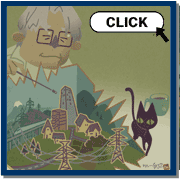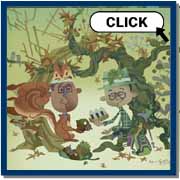毎年1月15日から21日は「防災とボランティア週間」。そして、毎年1月17日は「防災とボランティアの日」。
この日は1995年に発生した阪神・淡路大震災に因んで制定されました。
阪神・淡路大震災は、日本が初めて遭遇した甚大な都市型地震災害でした。建物が倒壊し、火災が同時多発的に起こりました。
この災害により、自助・共助の重要性を、またボランティア活動など外からの支援についても考える契機となりました。
自助・共助のひとつ、消防団。
東日本大震災でも、地域住民が自発的に組織した防災組織や消防団の活動は被害の拡大を防ぎ、その後の復旧にも大きな力を発揮しました。
消防団はかくも身近な存在ですが、よく知らないという方も多いのでは?
今回は、消防団で活動する社員がコメントをしてくれました。
【消防団の活動ってどんなもの?】
有事の際には消火活動はじめ、救助・避難誘導等を行います。
地理を良く知った地元の消防団員がいち早く現場に駆けつけ、初期消火にあたります。
その後は、消防署や警察機関等と連携を図り災害対応に努めます。
また災害時の対応に備え、日頃よりポンプ操法の訓練や機械器具点検を実施します。
その他では、予防消防として火防巡視や消火栓・防火水槽の点検、各家庭の消火器の点検等地域密着型の活動を行っています。
活動地域にもよりますが、水害や行方不明者の捜索等にもあたります。
消火のポイントは”慌てず落ち着いて行動”ですが、炎を目の前になかなか落ち着けないものです。
日頃より防災訓練への参加や避難経路・避難場所の確認をしておくことが大切です。
消火器の使い方をご紹介します。消火器の使い方は”ピン・ポン・パン”です。
① ピンで安全ピンを引き抜く。
② ポンでホースを外し、火元に向ける。
③ パンでレバーを強く握って手前から掃くように消火する。
また消火器は炎ではなく火元を狙って放射し、炎の吹き返しから逃れるため低い姿勢で消火。
怖いかもしれませんが、火元から1.5m~2m離れて放射しましょう。
住宅火災の場合では、消火器で対応できる目安は炎が天井に移るまでです。
炎が天井に移ったら、速やかに避難してください。
保管場所としては、誰もが見やすく取り出しやすい場所に置き、湿気や直射日光を避け転倒しない場所です。
キッチン付近に置かれる方もおりますが、玄関付近が良いとされています。
なるほど・・・。勉強になりました。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アジア航測は、私たちの技術が安全安心で豊かな社会に貢献できるよう、今後も活動を続けていきたいと考えております。


- ◎ バックナンバー
- ●「 2012防災週間特集」へ
- ●「夢の扉+のトビラ」へ
- ●「2012調布飛行場まつり特集」へ
- ●「エコ・ファースト特集」へ
- ●「アジア航測の航空機特集」へ
- ●「2013防災とボランティアの日特集」へ
- ●「特集 2013年未来へ ~3.11を忘れない~」へ
- ●「博物館へいこう! ~ その1 かわはく(埼玉県)~」へ
- ●「土砂災害防止月間特集」へ
- ●「夏休み特集トンボ博士にきく!」へ
- ●「 被災地モニタリング 始動!」へ
- ●「 Asia Air Survey Myanmar 開設」へ
- ●「4年目の復興へ ~未来・現在・過去のすべてをたいせつに~」へ
- ●「過去の災害から学ぶ ~ アジア航測の写真庫から ~」へ
- ●「「きわめびと」の“キワ” ~ササラダニを環境評価につかう 山腹工の定量評価~」へ
- ●「文化財3次元データの可能性 ~人のこころを癒す“3D”(奈良県立橿原考古学研究所 西藤清秀氏)~」へ
- ●「2014年防災の日特集 ~土地のリスクをきちんと知ろう~」へ
- ●「次世代の底ヂカラ」へ
- ●「博物館へいこう! ~ その2 横浜市歴史博物館 (神奈川県横浜市)~」へ
- ●「博物館へいこう! ~ その3 九州国立博物館 (福岡県太宰府市)~」へ
- ●「2016年防災とボランティアの日特集 ~ 1995年1月撮影 阪神地区モザイク写真 ~」へ