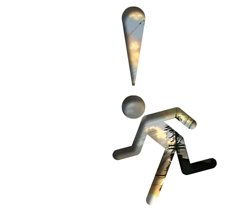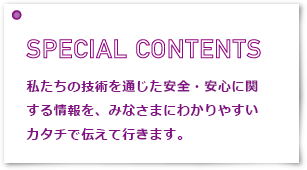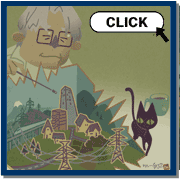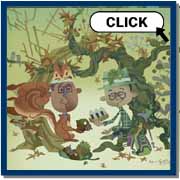ここに1枚の航空写真があります。今から54年前の5月24日にアジア航測が撮影したものです。
場所は大船渡、海上に流木や破壊された船などが散乱しているのが読み取れます。
チリ南部で、日本時間の1960(昭和35)年5月23日午前4時すぎ、マグニチュード9.5の超巨大地震が発生しました。
これにより生じた津波は平均時速750kmという高速で太平洋を横断し、24日午前3時ごろ日本列島に到達しました。
日本ではほとんど前触れのなかった遠地津波、「チリ地震津波」は、北海道から沖縄までの太平洋沿岸各地に被害を与えました。
特に三陸リアス海岸の湾奥に位置する岩手県・大船渡市(死者53人)と宮城県志津川町(同37人)の被害が甚大でした。
近海で起こる近地津波に比べ、周期が長く、大船渡湾では長周期波と共振して波動が増幅され、被害がさらに大きくなりました。
これをさかのぼること27年前、1933(昭和8)年に発生した三陸津波では、三陸沖地震の約30分後に三陸地方沿岸は津浪の襲来を受けました。
この時の復興計画報告書序言には、以下のとおり記載されています。
三陸地方に於ける津浪は十數年又は數十年の周期を以て繰り返し襲來するものなるを以て、右街路復舊工事及住宅適地造成事業の目的とする處は永久に浪災を防禦
し又は之を避け得べき安住の地を築設し、以て生活の安全と便益とを確保するにあるべきを以て、努めて姑息なる施設を避け、基本的計畫觀念を具體化せしむる方
針の下に各種の計畫を進めたり。(三陸津波に因る被害都町村の復興計画報告書,内務大臣官房都市計画課,1934-03-01 © 2003-2014 津波ディジタルライブラ
リィより引用 http://tsunami-dl.jp/)
「三陸地方に於ける津浪は十數年又は數十年の周期を以て繰り返し襲來するもの」。
自然の力は測り知れません。人間が行う防災の営みは、過去の被害や現況をつぶさに見、調べ、分析し、対策する、これの繰り返しです。
アジア航測は、測り知れない自然を、やはり「測」り、「見(診)」ることを原点に、これからも防災にとりくんでいきたいと思います。
アジア航測では、地震、台風や集中豪雨による河川氾濫、土砂災害などの自然災害が発生したとき、災害の状況を正確に把握することが防災・応急対策にとって
重要と考え、独自の判断により自社撮影を行っています。
また、撮影画像を用いたコンサルタント技術者による判読・解析、被災判読図や赤色立体画像の作成、合わせて全周囲映像の撮影もしています。
得られた情報は随時ホームページ上で公開しています。弊社技術が、現地の詳細解明ならびに二次災害の抑制に少しでもお役に立てれば幸いです。




- ◎ 関連リンク
- ●災害関連情報一覧|アジア航測株式会社
- ●防災きょうは何の日|アジア航測
- ●CSR活動|アジア航測株式会社