|
TOP > アジア航測の航空機特集 |
アジア航測は、戦後間もない昭和29年(1954年)2月に、荒廃した祖国再建のために「航測業が必要不可欠の事業である」という信念のもとに設立されました。この航空写真測量は今でも当社にとっての根幹事業となっています。 当社は現在ではレーザ測距技術を活用した航空レーザ測量技術も有していますが、設立当時は航空レーザ測量の技術は発明されておらず、航空写真測量を事業の中心として取り組んでいました。 写真測量とは、写真(画像)により可視化された対象物の種類や状況を解析し、その位置・立体的な形状・変化を対象物に直接触れずに、写真(画像)上で測量・調査し、各種地図等の地理情報空間を作成する技術です。 |
航空写真から地図をつくるために必要な機材は大きく3つに分けられます。 それは、空から地上を撮影するための「航空測量カメラ」、空から撮影した写真を地図化する「図化機」、そして空からの撮影を可能にする「航空機」です。 |

| 今回は、航空写真測量を行う上で不可欠な航空機やカメラ等、当社がかつて保有していた、また現在保有しているものまでをご紹介します。 まずは、航空測量カメラの紹介から! |
当社設立当初は、資本金のほとんどを高性能機材の購入に充てました。当社が日本で初めて導入したスイス・ウイルド社のアナログカメラであるRC5a全自動航空測量カメラは、当時世界最高といわれていました。会社設立から半年後の昭和29年9月に実施したRC5aによる撮影飛行は、初の自社カメラ運用として当社にとって記念すべきものとなっています。 その後、半世紀の間に様々な改良が加えられた機種が登場し、現在、当社でのアナログカメラは、RC30が現役として活躍しています。 |
RC30_1.png) |
|
| 当社が初めて導入したRC5aの後継機RC8(昭和31年に導入) 新百合本社の受付に展示中です! |
アナログカメラとしては現役で活躍中のRC30 |
~デジタル航空測量カメラの普及~
|
地図もCADやGISで数値データとして扱われるようになる中、コンパクトデジタルカメラが普及してきたように航空測量カメラもデジタル化が進みました。 今では当社の撮影でもデジタル航空カメラ(DMC)が活躍しています。 デジタル航空カメラは、カラー、モノクロ、近赤外の同時撮影ができ、一度のフライトで最大4,000枚の撮影が可能です。 |
DMC_1.png) デジタル航空カメラ(DMC) 本体重量は90kgほどあります |
| この航空測量カメラの航空機への搭載状況はこのようになっています。 |
RC30_2.jpg) |
|
| RC30の搭載状況 主な搭載機:セスナ206 |
デジタル航空カメラ(DMC)の搭載状況 主な搭載機:ガルフストリームコマンダー695 |
| レーザ計測機器の搭載状況 主な搭載機:セスナ208 |
機体の下から覗くとこのようになっています |
アナログカメラ(RC30)やデジタル航空カメラ(DMC)で撮影された写真をもとに、地形や地物を測定して地図としてつくりあげるのが図化機です。 この図化機も当初は大きな機械式でした。そして時代の流れと共にデジタル方式へと発展してきました。 |
|
~機械式図化機(1950~1980年代)~ 機械式図化機は、撮影された空中写真の位置関係や傾きをそのまま機械的に再現する構造になっています。航空写真を左右の投影台にセットし、両眼でそれぞれの写真を観測することで地形を正しく観測し、図面描画していきます。頑丈なボディーに多数の歯車、チェーン、シャフト、精密な光学機器からなりたっており、まさに"機械"という感じの装置です。 |
kikaishikizuka.jpg) |
|
~解析図化機(1980~1990年代)~ 精密写真座標測定器とコンピュータで構成され、航空写真の位置座標計算を、機械的な算出方法からコンピュータ解析計算で行えるようになったものです。航空写真を図化機にセットする手間が大幅に軽減されました。ソフトウェアと周辺機器の充実により、地形標高メッシュデータの計測を支援するプログラム等、様々な計測形態の要求に応えられるようになっています。 |
kaisekizukaki.jpg) |
|
~デジタル図化機(1990~現在)~ パソコンと立体視装置から構成され、簡単な操作で図面描画が可能です。使用する航空写真はデジタル化されていて、自動処理技術の発達により、従来の図化機に比べて大幅な省力化、効率化を実現しています。 現代の主力機となっており、当社製のデジタル図化機(ソフトウェア)の図化名人が国土地理院や多くの企業で使用されています。 |
航空写真測量で欠かすことができなのが航空機。 アジア航測では調布飛行場と八尾空港を起点に航空機6機を保有して日本全国の航空写真撮影やレーザ計測ができるようになっています(2012年12月現在)。 飛行機といっても機種ごとにそれぞれの特性があり、その特性に合わせてデジタル航空カメラ、アナログカメラ、レーザ計測機器を機体に搭載しています。アジア航測では設立時から今日までの多くの航空機が活躍してきました。 ここからは1954年設立時から現在までに導入・活躍した航空機を紹介していきます。 |
| デ・ハビラントカナダ式ビーバー機(JA3080) |
| 1954年12月に導入された機体、自社保有機による撮影の初号機となりました。しかし、当時は航空事業免許がなかったため、一時期運航を委託していました。 1956年に当時の運輸省から免許が下り、自社運航が始まりました。 |
JA3080_1.jpg) |
JA3080_2.jpg) |
| デ・ハビラントカナダ式ビーバー機(JA3080) | |
| ビーチクラフト式C185型(JA5032) |
| 1957年、撮影作業の増大に対応するため、米軍払下げのビーチクラフト式C185型を導入しました。 |
JA5032.jpg) |
| ビーチクラフト式C185型(JA5032) |
| エアロコマンダー式680E型(JA5073) |
| 1960年に、新鋭双発機として導入され、翌年3月から撮影作業に配備された機体です。このコマンダー双発機は航空撮影に極めて適していたので、撮影効率が飛躍的に向上しました。この後継機種となるガルフストリームコマンダー695(2機)は、現在我が社の主力機として今もなお活躍しています。 |
JA5073.jpg) |
| エアロコマンダー式680E型(JA5073) |
| エアロコマンダー式680E型(JA5074) |
| 1962年、老朽化したビーチクラフト式C185型の入れ替え機として導入されました。このJA5074は1996年に退役し、その後は成田空港に隣接している航空科学博物館へ寄贈されました。屋外展示場に展示されおり、今でも見ることができます。なお、料金300円で"搭乗"することができます! |
JA5074_1.jpg) |
|
| エアロコマンダー式680E型(JA5074) | 航空科学博物館に展示中のエアロコマンダー680E |
| セスナ式U206C型(JA3340) |
| 1967年、撮影業務の増大に対応するため導入されました。この時点では、自社機は4機となり、航測業としては当時東洋一の規模でした。 |
JA3340.jpg) |
| セスナ式U206C型(JA3340) |
| エアロコマンダー式685型(JA5215) |
| 1973年、マルチバンドカメラの環境調査への適用、リモートセンシング技術の利用など、新需要の増加に対応するため、新鋭撮影用航空機として導入されました。この機体は、航続時間、航続距離ともに680E型の約2倍の能力を有しているだけでなく、特殊な撮影にも対応可能でした。 |
JA5215.jpg) |
| エアロコマンダー式685型(JA5215) |
| セスナ式TU206型(JA3856) 現在運航中 |
| 1979年、同型機であるJA3340との入れ替え機として導入されました。この機体は導入されてから30年以上経過した今もなお、現役でアジア航測で活躍しています! とても小回りが利くので、撮影コースが蛇行する道路や鉄道などの路線測量に力を発揮しています。 |
| セスナ式TU206型(JA3856) | |
| セスナ式TU206型スペック | |
| 出 力: | 310SHP×1 |
| 乗 員: | 最大6名(操縦士含む) |
| 航続距離: | 895km |
| 搭載機器: | RC30withPOS |
| 活動範囲: | 本邦一円(遠方近年実績:北海道) |
| ガルフストリームコマンダー式695型(JA8600) 現在運航中 |
| 1995年に導入されました。双発ターボプロップ機で与圧キャビンを有する高速機、国内では保有しているのはアジア航測のみです。 従来のエアロコマンダーと比べて巡航速度は1.7倍の560km/h、航続距離は約2倍の3,800km、撮影可能最高高度は9,000mで、あらゆる飛行領域で安定しています。 阪神淡路大震災では被災直後の様子を撮影し、唯一、当社のこの機種だけが発災当日のうちに東京まで写真を届け、全国のテレビ、新聞に情報を伝えることができました。 |
| ガルフストリームコマンダー式695型(JA8600) | |
| ガルフストリームコマンダー式695型(JA860A) 現在運航中 |
| JA8600と同型機で、2008年に導入されました。東日本大震災ではこのJA860Aがデジタル航空カメラで航空写真撮影を行いました。 JA8600とともに、日々撮影業務に対応しており、その活動範囲は北海道から沖縄県石垣島、そして小笠原諸島にわたっています。 日本に2機しか存在しないアジア航測のガルフストリームコマンダー695。この貴重な機体を見かけた際は、ぜひカメラに納めてください! 当社社員のパイロット、撮影士、整備士、皆がとても喜びます! |
| ガルフストリームコマンダー式695型(JA860A) | |
| ガルフストリームコマンダー式695型スペック | |
| 出 力: | 940SHP×2 |
| 乗 員: | 最大10名(操縦士含む) |
| 航続距離: | 3,700km |
| 搭載機器: | RC30withPOS、DMC、航跡記録 |
| 活動範囲: | 本邦一円(遠方近年実績:北海道、石垣島、小笠原諸島) |
| セスナ式208型(JA8229)(JA8890) 現在運航中 |
| 2009年、それまで年間チャーターしていた航空機をデータ収集体制強化のために購入しました。セスナ208を2機導入したことにより、データ収集業務の大半を自社で行うことが可能となりました。 東日本大震災では両機ともにレーザ計測によるデータ収集で活躍しました。 |
| セスナ式208型(JA8229) |
|
| セスナ式208型(JA8890) | |
| セスナ式208型スペック | |
| 出 力: | 600SHP×1 |
| 乗 員: | 最大9名(操縦士含む) |
| 航続距離: | 1,797km |
| 搭載機器: | RC30withPOS、DMC、レーザ |
| 活動範囲: | 本邦一円(遠方近年実績:北海道、石垣島) |
| 新規機体の導入 近日公開! |
| アジア航測では新規機体の導入に向けて準備を進めています。その機体はアメリカで製造されたばかりで、先日、日本に到着したばかりです! この模様は後日アップします。お楽しみに! |
JA_x.png) |
|
| 新たに導入する機体の正体は!? | |
~おわりに~
| 先日、当社の運航所が置かれている調布飛行場と八尾空港を訪れました。そこには、当社事業の前提となる航空事業の安全を確保するという、自分たちの仕事に対して誰よりも誇りと責任をもって取り組む社員たちの姿がありました。 |
| 航空機の安全は当社整備士の日々の確実な整備作業によって支えられ、その上で様々な写真撮影やレーザ計測などの活動の安全な遂行がはじめて成り立っています。
機体整備に汗を流す様子を目の当たりにしたときは、普段見慣れない光景だったので、自分の会社ではないような気がしました。当社整備士をクローズアップした記事を今後、掲載したいと思っております。 |
オリジナル・コンテンツ (特集刊行にあわせて更新します)
 |
千葉センセイの 凸凹ばなし |
 |
今村センセイ 地震たて横ナナメ |
 |
空とぶ森と みずと大地とNEW! |
 |
地球みつめ隊 がゆく!NEW! |
 |
 |
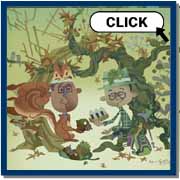 |
 |
||||
 |
世界を災害から守る! 赤い地図革命あれこれ |
 |
安全な地盤って? 地質ってなに? |
 |
森と水と大地をこよなく 愛す仲間たち |
 |
アジア航測の熱い想いを 長尾レポーターが追う! |
 |
今回のテーマは! 「渋谷の凸凹」 |
 |
今回のテーマは! |  |
今回のテーマは! |  |
今回のテーマは! 「空から未来を創造 熱い社員を追う!」 |
 |
バックナンバー |
| 「 2012防災週間特集」へ | |
| 「 2012調布飛行場まつり特集」へ | |
| 「エコ・ファースト特集」へ |