海外作業第一号
昭和39年(1964)の東京オリンピックの閉幕直後から、景気は降下の一途をたどり不況のどん底に引き込まれました。日本産業のけん引役を果たしてきた鉄鋼業界では、大型倒産が相次ぐなど日本経済は戦後最大と言われる苦境にみまわれることとなりました。
このような状況下で、再び社長に就任した柳沢米吉は、営業部門と技術部門が緊密化、一体化することによって業務の質を高めるとともに、事務の効率化や経費節減など経営の合理化を図る一方で、受注の確保と拡大を求めて海外の新市場開拓という方針を打ち出し、南ベトナムやガーナ、クウェートなどへのアプローチを開始しました。
翌昭和40年(1965)4月には、海外作業第1 号となるガーナでの基準点測量を受注しました。この業務は当社の海外事業のテストケースとして取り組むことになりましたが、良好な結果を納めることができました。

-e1694440885925.jpg)
(昭和40年)
クウェート国航空写真測量を国際入札にて受注
昭和51年(1976)4月、初の海外プロジェクトとしてクウェート全土の航空写真測量を国際入札により落札しました。その後、クウェート市庁に対して地下埋設物の図面作成を提案したところ、「クウェート公共施設データ管理システム(Kuwait Utility Data Management System、略称KUDAMS)」という大規模なプロジェクトに発展しました。
昭和58年(1983)8月、現地測量隊の第1陣55名が出発しました。航空撮影用のセスナ機は、分解して船積みし、現地で組み立てました。撮影に際して使用できる既製の地図がなかったため、あらかじめ縮尺1/20,000で撮影を行って作成した写真図をもとに本撮影を行いました。
一方、日本国内でも110名が作業に当たりました。最先端の機器を駆使した世界最初の大規模デジタルマッピングにより、クウェート全域580㎢の1/500地形図を作成し、各種地下埋設物を記述したユーティリティデータベースを構築していきました。
このプロジェクトは規模の大きさもさることながら、測量業界が指向していた最先端のGIS(地理情報システム)であったため、技術面でも初分野への挑戦が連続しました。完成後、世界初の本格的な施設管理システムとして、国際学会や実業界から高い評価を得ることができました。

インドネシアでの事業拡大
当社の海外事業は、インドネシアを中心に順調な伸びを示しました。民需では、日本の大手商社が現地で手がけていた森林開発に関連して、航空写真撮影、基準点測量、森林判読、図化作業などを担当しました。昭和51年(1976) には、OTCA の後身であるJ ICA (国際協力事業団 現・独立行政法人国際協力機構)の依頼により、インドネシア南スラウェシ州中部で水資源総合開発計画のための航空写真測量を行い、昭和53年(1978)には、同国のサグリンダム地区での建設関連事業に際して施工管理を受注しました。
国家間レベルの技術協力で、当社が大きな役割を果たした事業もありました。昭和52年(1977)3月、同国公共事業省統計情報処理局から、灌漑網整備や、移住のための農業適地調査といった農業開発等のためのリモートセンシングに関して国際協力の要請がありました。当社が基本設計を行うとともに、提案書を作成しました。その結果、昭和55年(1980)4月から5年間にわたって、同プロジェクトが実施されることになりました。日本側が実施した具体的な協力内容は以下の通りでした。
- 農業開発のためのリモートセンシング・データのアナログおよび
デジタルの画像処理システムの供与と専門家の派遣 - インドネシア技術者の日本での研修
- 航空写真の撮影、現地調査など一連の技術協力
贈呈式(昭和49年)2-e1694441088943.jpg)
贈呈式(昭和49年)

サウジアラビア国土基本図を作成
昭和53 年(1978)5 月には、サウジアラピアの首都、リヤドを中心とするカッシム地方12 万1,000㎢ の、1/50,000 および1/250,000 国土基本図を作成するプロジェクトを国際入札で落札しました。クウェートに次ぐ、海外大型プロジェクトでした。作業は6年に及びましたが、現地調査から印刷・編集まで、地図作りを一貫して行うことは貴重な経験であり、技術を蓄積することができました。
昭和57年(1982)11 月からは、カッシム地方の作業と並行しながらウエストルブアルカリ地区7万9,100㎢の基本図作成にも着手し、翌年5月に現地作業を終了しました。
-e1694673859685.jpg)
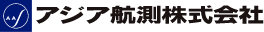
贈呈式(昭和49年).jpg)
-332x332.jpg)
-332x332.jpg)
-332x332.jpg)
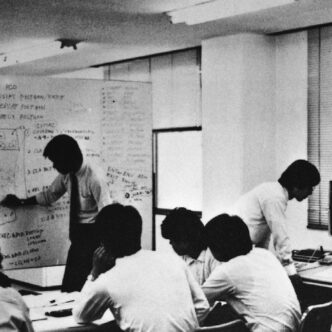
-332x332.jpg)
-332x332.jpg)
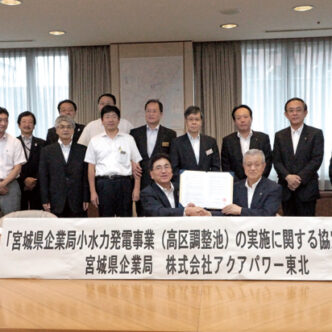
 大船渡港-332x332.jpg)
-332x332.jpg)